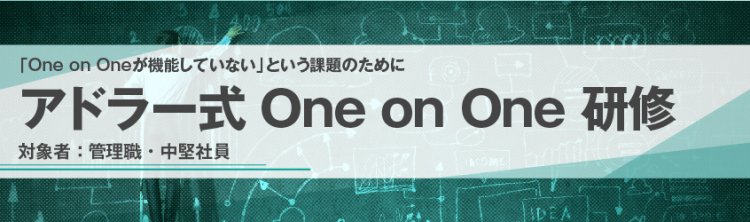共同体感覚
共同体感覚とは、アドラー心理学における中心概念であり、「自分は社会の一員であり、他者とつながり、貢献できる存在だ」という感覚を指します。この感覚が高い人は、他者と協力し、信頼関係を築きながら、自律的に行動できます。組織においては、共同体感覚が高い状態が「心理的安全性」や「エンゲージメント」の基盤となり、チームの成果や人材育成にも大きく影響します。
実務上の重要性や活用場面
ビジネスの現場では、信頼と協働が不可欠です。共同体感覚が高い従業員は、他者を敵や競争相手と見なさず、目的達成のために自然と協力的な行動を取ります。また、「役に立っている」という実感があることで、内発的動機づけや働きがいの向上にもつながります。メンバー同士の対立や孤立を防ぎ、離職防止や心理的安全性の醸成にも効果的です。
研修や組織開発の中での位置づけや具体例
共同体感覚は、リーダーシップ研修やコミュニケーション研修のテーマとしても非常に有効です。たとえば、アドラー心理学を基盤にしたマネジメント研修では、叱責や競争ではなく、共感と信頼によるチーム運営の重要性が扱われます。また、1on1ミーティングの質向上やフィードバック文化の定着にも、共同体感覚の理解が求められます。組織開発の文脈では、心理的安全性の土台として共同体感覚を強化するアプローチが注目されています。
関連キーワード(類語、略語、英語表記など)
アドラー心理学/共同体意識/つながり感/社会貢献意識
コミュニティ・フィーリング(Community Feeling)/心理的安全性/信頼関係/協働意識/帰属意識
エンゲージメント/1on1/職場の人間関係/貢献感/承認欲求
共同体感覚は、**組織の土台となる「人と人とのつながり」**を支える重要な考え方です。企業研修や人材育成の現場で、アドラー心理学の実践知として導入することで、信頼と協力にあふれた職場づくりが可能になります。人事・研修担当者や経営者にとっては、組織の持続的成長を支えるキーワードとして理解と活用が不可欠です。